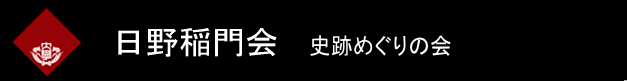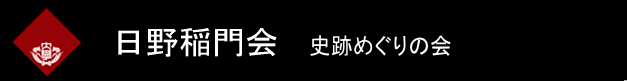|
トップページにもどる
第1回日野稲門会史跡めぐりの会
|
投稿日 2018年10月17日 |
第1回日野稲門会史跡めぐりの会(報告)
1.実施日:2018年9月23日(日)曇り
2.実施場所:高幡不動尊明王院金剛寺境内
3.めぐり箇所:玉南鉄道碑→仁王門→不動堂→奥殿(寺宝展)→文永の板碑→大日堂(鳴り龍)→ 藤蔵の墓→句碑→不動ケ丘高幡城址→山内八十八カ所の路→四季の道→五重塔
4.参加者:青木孝則、麻生貞雄、石川宏、井上敬三、大田吉彦、大西ご夫妻、京極英二、小松靖幸、阪本昭夫、杉本武彦、鈴木武彦、??田俊雄、高橋敏夫、永山肇、生川博、本間崇夫、町谷ご夫妻、南正隆、宮本誠二、小笠原豊、上田實、村山友宏 以上24名(敬称略、五十音順)
5.リーダー:村山友宏、サブリーダー:小笠原豊、上田實、写真担当:高橋敏夫
6.案内解説:当山金剛寺僧侶 百戸祐大、日野市生涯学習課文化財係 中山弘樹
7.概要:お彼岸の中日、9月23日、土方歳三像脇に午前9時に全員が集合。冒頭挨拶で小笠原会長より、この同好会発足の経緯(アンケート結果、要望第1位だったこと等)の説明があり、村山リーダーより本日の行程が説明され、当初予定した土方歳三記念館が当日休館のため、新選組関係は次回以降に回すこと等が伝えられた。

最初に玉南鉄道碑について、詳しい石川宏氏(日野稲門会役員)より解説。当時府中が終点であった京王線を、多摩川の南の篤志家が金を出し合い、八王子まで延長したことがこの碑に記されている。
次に本日ご参加頂いた市職員の文化財係中山氏(早大文学部OB)から、文化財についてのお話を伺う。
解説は以下、仁王門(重文指定)について、これが室町時代に建立され、昭和34年に解体修復されたことやその建築の特徴等について、また不動堂(重文指定)は平安時代初期、慈覚大師円仁が清和天皇の勅願によって建立された都内に現存する最古の建造物で、中世真言密教系の堂の姿をよく伝えている。その元は、8世紀の大宝年間に創建されたと伝えられる。 当山は、戦国武将に尊崇され、江戸時代には真言宗智山派別格本山の寺院として門末36箇寺を擁する関東屈指の大寺院であり、広く庶民の信仰をあつめ、古来から関東三不動の1つとされてきた。今も年中この不動堂で護摩法要が執り行われている。
次に当山僧侶百戸祐大様に奥殿(おくでん)一階に案内され、展示された寺宝や古文書について解説を受けた。ここは、平安時代に創られた重文で、古来日本一といわれる「丈六不動三尊」という巨像(像高285cm、重量1100キロ)が安置されている。平安後期、造立に関わった屈強な関東武士(西氏1族ら=武蔵七党の1つ)の気分を彷彿とさせる豪快な不動明王の姿である。さらにここには、仏舎利はじめ、貴重な仏画・書画・工芸・古文書が多数展示されており、土方文書や新選組資料も展示されていて、歴史動向や地域社会との関わりがよく分り、興趣が尽きない。灯台下暗し、必見の価値があった。
次も、僧侶の案内で当山総本堂である大日堂に入り、金剛界大日如来像を拝観し、有名な「鳴り龍」天井に一人ずつ手を打ち響きに耳を澄ます。
次に中山氏の案内で、大日堂の奥にある墓地に「藤蔵の墓」を訪ねた。江戸時代の国学者平田篤胤がその著で紹介し、小泉八雲がその著で広めた事件で、藤蔵が「ほどくぼ小僧(勝五郎)」の前世だったという『生れ変わり物語』にまつわる話で、これは江戸にも評判となり、外国にも伝わったという。
このあと、境内にある比高50mほどの裏山にのぼり、高幡城祉を訪ねた。文献が乏しく築城年は不明だが、15世紀頃、上杉、北条、足利らの分倍河原の合戦の時の拠点になったのでは、ともいわれ、闘いに敗れた上杉憲顯がこの山に逃げ込み自害したという、その祠堂が奥殿の横にある。そこで北条氏照の家臣の高幡氏平山氏の居城だったのでは、とも言われる。のちに秀吉の小田原攻めの際、攻めよせる前田利家から城を守ったのが高幡氏だとも言われる。山上からは日野市街地が見渡せ、その眺望に一同感嘆した。帰路は、山内八十八カ所巡りの小径を辿り、10万本という彼岸花の咲き誇る中を下山した。
千年にわたる信仰の聖地は、この秋色いっぱいの彼岸花におおわれ、しばし俗世を忘れる史跡めぐりでした。
クイズを出したあと、上田リーダーの挨拶で閉会。12時散会の後、有志で門前の「開運そば」で反省会兼ねて昼食。
*なお、時間がなく、巡ることができなかった句碑、歌碑を以下に列挙します。松尾芭蕉、山口誓子、鍵和田柚子、皆川盤水、村沢夏風、鏡水、石田波郷、??橋悦男、清崎敏郎、有山薫糸、宮柊二、野村清 (碑文内容の詳しい解説は、webサイト「高幡不動尊の文学碑」でご覧下さい。)
文責村山

|
|
|
|
|
 |